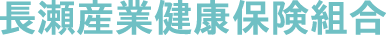特定保健指導
特定健診の結果より、生活習慣を見直し、健康の保持に努めていくのに適切な支援が必要とされる人には、医師や保健師等の専門知識を有する人による特定保健指導が受けられます。
高血糖、高血圧、脂質異常が生活習慣病となる前の方が対象です。
糖尿病、高血圧症、脂質異常症の薬を服用している人は、特定保健指導の対象外となります。
対象者
腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上もしくはBMIが25以上で、以下の3項目のうち1項目でも該当する方
| 高血糖 | 脂質異常 | 高血圧 |
|---|---|---|
| 空腹時血糖(やむを得ない場合は随時血糖)が100mg/dl以上または、HbA1c(NGSP値)が5.6%以上 | 空腹時中性脂肪(TG)が150mg/dl以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175mg/dl以上)またはHDLコレステロールが40mg/dl未満 | 収縮血圧(最高血圧)が130mmHg以上、または拡張期血圧(最低血圧)が85mmHg以上 |
階層化
特定健診の結果からリスクに応じて、「積極的支援」と「動機づけ支援」に階層化します。 また、特定健診受診者で、気をつける項目がある方には、パンフレットなどによる生活習慣改善への情報提供が行われます
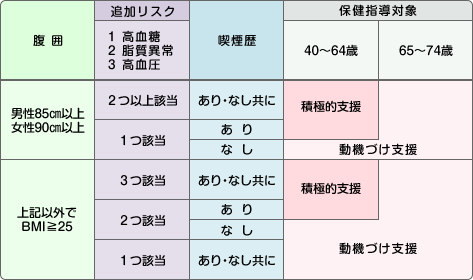
保健指導機関
基本的に健診を受けた健診機関で特定保健指導を行いますが、特定保健指導を実施していない場合は、健保組合指定の指導機関になります。
保健指導内容
実施する保健指導機関によって内容は若干違いますが、おおむね以下の手順で行われます。
| 動機づけ支援 | 原則1回のフォロー 初回面接(約40分)で、実行可能な生活習慣改善の行動計画を対象者とともに作成し、自己管理にて6ヵ月後に現状を確かめ評価します。 |
|---|---|
| 積極的支援 | 3ヵ月以上、複数回にわたってフォロー 初回面接(約40分)で実行可能な生活習慣改善の行動計画を対象者とともに作成する。その後3ヵ月以上継続して、メールや電話などで生活習慣のフォローを受け、6ヵ月後に現状を確かめ評価します。 |
費用負担
健保組合負担
- ※ただし、ご連絡がなくキャンセルされた場合、委託先からのキャンセル料を請求させていただくことがあります。
利用手順
- ①健保組合から、特定保健指導対象者に個別の案内を送ります。
- ②案内に入っている申込用紙に指導希望日を記入し、健保組合へ送ってください。
- ③健保組合で指導日時の予約を取り、場所と時間等をご連絡します。
- ※会社によっては、まとめてのご案内となることもあります。